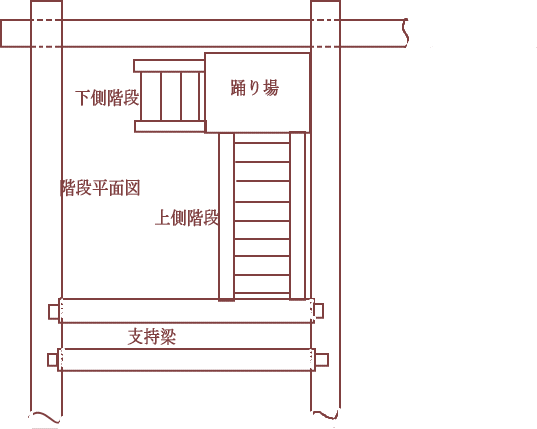
まず、支持梁2本を最上段の中央ログと西側ログに掛け渡して上側の踊り場を造り、続いて下側の踊り場を造る。そして下側の踊り場に下側階段を掛け、上側の階段に上側階段を掛ける。
なお、最初は下側階段をいきなり中央ログに掛ける予定であったが、この部分にトイレ棟へのドアを設けた
ため、図のような90度折れ曲がりタイプに設計変更した。その結果、上記の支持梁が必要になった。

先ずは支持梁の設置。支持梁りの両端にホゾを突出するよう形成し、西側ログと中央ログの上面にホゾ溝を形成する。そして支持梁をチェンブロックで吊り、両端のホゾをホゾ溝に落とし込んで嵌合させる。これで上側の踊り場ができ、これに上側階段を掛けることができる。
なお、最初から2階の床梁(写真に見えている2本)を1m位延長しておけば2階の踊り場部分がかなりスマートになったはず。上述のように途中で設計変更したため、これもかなわず、残念。

続いて、下側の踊り場を造る。足場金物の向こうの隅に見えているのがそれ。

下側階段。上端と下端の踏板のホゾを外側に貫通させて、その外方突出部に丸棒のキーを打ち込んで固定している。残念ながら、左側の桁はホゾを貫通させる際に2つに割れてしまった。裏側(向こう側)に補強プレートを当てて、ねじ止めした。

上側階段の桁。丸太を半割りした物を使用している。上下端にホゾ穴を貫通させて開け、これに上端、下端の踏板の両端に形成したホゾを貫通させ、外側への突出部にキーを打ち込んで固定した。この点は下側階段と同じ構造にした。但し間の踏み板は、桁の内面に8組のスリット溝を形成しておき、これを上側の踊り場に掛け、この状態で間の踏み板を上記スリット溝に差し込むこととした。

上側階段の下端部の様子を示す。
下端の踏み板の外方突出部が丸棒キー(木の枝)で固定されている様子やその上の踏み板がスリット溝に差し込まれている様子がわかる。
三角形状のものは、セトリング吸収構造を構成している楔である。これは踊り場の上面に堀り込まれたガイド溝内にスライダ可能に配置されている。この楔を左側にスライドさせることで、階段の支持点の高さが低くなり、もってセトリングを吸収できるのである。

上側階段の上端部の様子を示す。
上端部は16mmの貫通ボルトで支持梁の側面の固定されている。支持梁の端部が中央ログに嵌め込まれている様子が判る。手前に見えるのは2階の床。